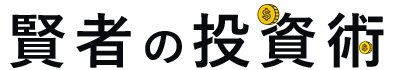人はいつも合理的な判断をしているとは限りません。特に投資のように損益が関わる場面では、感情によるバイアスが判断を狂わせることがあります。
その代表的な理論が「プロスペクト理論」です。投資判断を支える基礎知識として、この理論の仕組みと心理的作用について理解を深めていきましょう。
プロスペクト理論とは
プロスペクト理論とは、「人は損失を避けたいという気持ちが強すぎるあまり、非合理的な判断をしてしまう」という意思決定に関する理論です。1979年に心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって提唱され、2002年にはカーネマンがノーベル経済学賞を受賞したことでも知られています。
この理論は、行動経済学の代表的な理論の一つであり、特に投資や購買行動における心理的なバイアスを説明する上で欠かせない考え方です。たとえば、同じ金額を得る場合と失う場合では、人は損をすることの方により強く反応します。つまり「得る喜び」よりも「損する苦しみ」の方が大きく感じられるというわけです。
このような人間の非合理的な判断は、投資判断にも大きな影響を与えます。冷静なはずの判断が、実は感情に大きく左右されていることを理解することが、成功する投資家への第一歩となります。
心理的作用
プロスペクト理論には、主に以下の3つの心理的作用が含まれています。これらはすべて、投資家の判断を狂わせる原因となりうるものです。
損失回避性
もっとも代表的なのが「損失回避性」です。これは、人は得をすることよりも損をすることを避けたがる傾向があるというものです。たとえば、「この商品を買えば年間3万円の得になる」よりも「この商品を買わないと年間3万円の損をする」と伝えた方が、消費者の心に強く響きます。投資においても、含み損を抱えている株をなかなか売却できない心理や、少しの利益で早々に売ってしまう行動は、この損失回避性によるものです。
参照点依存性
人は価値を絶対値で判断するのではなく、自分の基準(参照点)と比較して判断する傾向があります。たとえば、株価が1000円から1200円に上がった後に1100円まで下がると「損をした」と感じるかもしれませんが、実際には購入価格より利益が出ているケースもあります。このように、過去の価格や購入時の価格を基準に損得を判断してしまうのが、参照点依存性の特徴です。
感応度逓減性
同じ金額の損失や利益でも、金額の大小によって感じ方に差が出るのが「感応度逓減性」です。たとえば、1000円の買い物で200円安くなると「得をした」と感じやすいですが、10万円の買い物で同じ200円の値引きでは「大した差ではない」と感じることが多いです。投資額が大きくなるほど、小さな変動に対する感情の動きが鈍くなる傾向があります。
投資判断への影響
これらの心理作用は、冷静で合理的な判断を必要とする投資の場面で、思わぬミスを引き起こす要因となります。過去の損失に固執して適切なタイミングで損切りできなかったり、割高とわかっていても「買い逃す恐怖」にかられてエントリーしてしまったりといった行動が典型的です。
プロスペクト理論を理解し、自分自身の判断が感情に左右されていないかを意識することが、安定した投資成績を実現するための鍵となるでしょう。